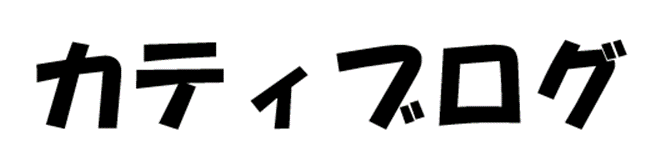薬師如来は7世紀頃から人々に広まり、病気を治し健康を維持する仏として信仰されてきました。
人は誰でも病気にかかり、また周囲には必ず病気で苦しんでいる人がいて、薬師如来の信仰で気持ちが強く持てたらそれが御利益(ごりやく)だと思います。
薬師如来は左手に薬壷(やっこ)を持っているという特徴があります。
また薬壷(やっこ)を持っていないこともあります。
①【薬師如来 浄瑠璃(じょうるり)浄土に住む病気を治す仏】薬師如来とは

薬師如来は病気を治す如来で、阿弥陀如来が未来の為の如来であるのに対し、薬師如来は現世の為の如来で、別名を薬師瑠璃光如来(やくしるりこうにょらい)ともいいます。
そして阿弥陀如来が浄土の西方(さいほう)十万憶の仏国土のかなたにある極楽浄土で命あるもの全てを救う仏様であるのに対し、薬師如来は浄土の東方(とうほう)十万憶の仏国土のかなたにある浄瑠璃(じょうるり)浄土に住み、病気を治す仏様として存在し人々に信仰されてきました。
浄瑠璃(じょうるり)浄土とは、薬師如来の浄土として瑠璃(るり/七宝 しっぽう)の一つで、青い奇麗な宝石)が大地で、建物や物品の全てが七宝(しっぽう)でできています。
七宝(しっぽう)とは仏語で、七種の宝石のことで、金・銀・瑠璃(るり)・玻璃(はり/水晶のこと)・硨磲(しゃこ/シャコガイ)・珊瑚(さんご)・瑪瑙(めのう/オパール/蛋白石 たんぱくせき)のことをいいます。
仏教が日本に伝わったのは 552年に百済(くだら/4世紀前半から660年にかけての古代の朝鮮半島の国家)の聖明王(せいめいおう/仏教を尊んだ百済第26代の王)が朝廷に、釈迦像と経典を献上された時とされています。
その後薬師如来は7世紀頃から、病気の平癒(へいゆ 治ること)と健康維持のための仏様として信仰されていました。
薬師如来は薬師三尊像として脇侍(わきじ)を伴い、向かって右側に日光菩薩、向かって左側に月光菩薩が配置され、三体を一組とされることが多いです。
また薬師如来には薬師如来に仕える12の武神がいて、12の武神は12の干支・月・方角を守るとされています。
昼間は日光菩薩が薬師如来を守り、夜間は月光菩薩が薬師如来を守り、12の武神が絶えず薬師如来を守り続けています。

飛鳥時代(592年~710年)の680年に天武天皇により建てられた薬師寺(奈良県奈良市)の金堂には、薬師三尊像(銅製の坐像)が置かれており、国宝に指定されていて世界文化遺産です。
薬師寺は法相宗(ほっそうしゅう/大乗仏教)大本山(だいほんざん)薬師寺といいます。
法相宗(ほっそうしゅう)の大本山(だいほんざん)は薬師寺と興福寺(奈良県奈良市)で、どちらも法相宗(ほっそうしゅう)の総本山です。
薬師寺の薬師三尊像は薬師如来の像の高さは 2.547mあり、現在は造られた当時の黄金色は剥がれ黒光りしています。
薬師如来のシンボルの薬壷(やっこ)を持つようになったのは平安時代からなので、薬師寺の薬師如来は薬壷(やっこ)を持っていません。
薬師如来は如来であるため衣服も質素で、宝飾品も付けていません。

有名な薬師如来として、飛鳥時代607年に聖徳太子によって建てられた法隆寺(奈良県生駒郡 いこまぐん 斑鳩 いかるが)の国宝の金堂に、銅製で国宝の薬師如来坐像があります。
また奈良時代747年聖武天皇の病気が治ることを願って光明(こうみょう)皇后によって建てられた新薬師寺(奈良県奈良市)本堂に、木製で国宝の薬師如来坐像があります。
②【薬師如来 浄瑠璃(じょうるり)浄土に住む病気を治す仏】特徴

薬壷(やっこ):全ての人々の病気を治す万能薬が入っている薬壷(やっこ)は薬師如来の持ち物の唯一の特徴です。
左手を下に下げ膝の上の手のひらを上にして薬壷(やっこ)を持っています。
薬壷(やっこ)を持っていない場合は、左手を下げ左膝の上で左の手のひらを上向きにした与願印(よがんいん)の印相(いんそう)で、人々の願いを聞き叶えるという意味を表します。
螺髪(らほつ):髪型は螺髪(らほつ)というパンチパーマのように見える全ての髪の毛が細かいぐるぐる巻きになった髪型です。
肉髻(にっけい):頭の上に肉髻(にっけい)という盛り上がりがあります。
これは髪の毛を膨らませて盛り上がりをつけているのではなく、悟りを開いた人の象徴のお姿として頭の上が二段になっているのです。
螺髪(らほつ)と肉髻(にっけい)は、薬師如来が智慧(ちえ)に優れていて、智慧(ちえ)が詰まっていることを表しています。
肉髻珠(にっけいしゅ):肉髻(にっけい)の前面の根元に付いている朱色の部分で、薬師如来の智慧(ちえ)の光を表している珠(たま)です。
白毫(びゃくごう):毫(ごう)とは少し、わずか という意味です。
三道(さんどう):首にある三本の横向きの皺(しわ)で、ふくよかさを表しています。
衲衣(のうい):衲(のう)は衣という意味で、粗末な袈裟(けさ)のことです。
袈裟(けさ)はインド仏教の修行者と他の宗教の修行者を区別するために用いられた僧侶が身に付ける布状の衣装のことです。
袈裟(けさ)はもともと赤褐色であったことから古代インド語で赤褐色のことをカーシャーヤといい、カーシャーヤの音写として袈裟(けさ)となりました。
施無畏印(せむいいん):右手を前に出し上に曲げて、手のひらを上向きで外側に向けた印相(いんそう)のことで、人々に対し畏れなくていいという人々を安心させる意味があります。
薬指を少し前に出し、人々に与える安心感をより強めています。
結跏趺坐(けっかふざ):片方の足の甲を反対側の太ももの上に乗せる座り方です。
結跏趺坐(けっかふざ)は坐像でよくみられる座り方です。
化仏(けぶつ):光背の二重円相光(にじゅうえんそうこう)に付いている薬師如来を助ける小さい仏様のことをいいます。
二重円相光(にじゅうえんそうこう):頭から光を出す頭光(ずこう)と、身体から光を出す身光(しんこう)を合わせた光背(こうはい)のことです。
蓮華座(れんげざ):仏教の花であるインド原産の、泥の中から奇麗に咲く蓮の花びらで形造られた台座です。
③【薬師如来 浄瑠璃(じょうるり)浄土に住む病気を治す仏】まとめ

人は一生のうちに何度も病気になるもので、また身近な大切な人が病気になっても自分の事と同じように心配で苦しいものです。
薬師如来を信仰することで、少しでも気持ちが和らぎ、心強く思えたら御利益(ごりやく)があったということだと思います。
病は気からと言いますが、本当にその通りだと思います。